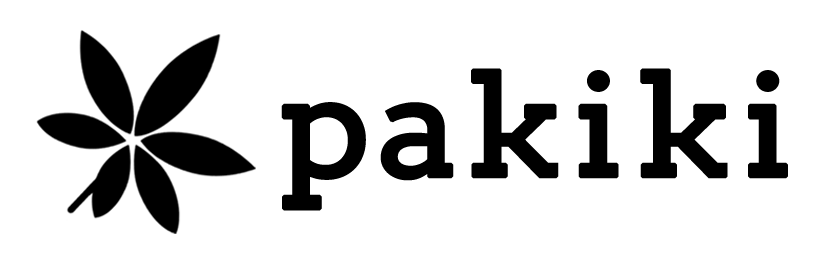2024年6月にお迎えした「ビカクシダ・キッチャクード」の育て方・成長記録・特徴を初心者向けにまとめたページです。随時更新していきますので、これから育てたい買いたいと思っている方はご参考になさってください。

ビカクシダの購入はメルカリがおすすめ!
私はビカクシダのほとんどをメルカリで購入しています。
出品者の評価・発送地域をチェックし、株や胞子の入手先をきちんと確認した上で購入すれば安心です。
ビカクシダ・キッチャクードとは?特徴など

ビカクシダ・キッチャクードの特徴
ビカクシダ・キッチャクードはその独特のフォルムが特徴的なビカクシダです。中でも特徴的なのは貯水葉で「キャベツ」などと呼ばれることもあり葉脈の凹凸が深いです。ちなみに愛称的に「キッチャ」と呼ばれることも多く、私もそう呼んでいるひとりです。
また、個体差が激しい品種でもあり、特にその個体差が現れるのが胞子葉です。先端が細かく枝分かれ(分岐)する特徴は共通していますが、リドレイ寄りの性質が強い個体であれば上向きに立ち上がり、コロナリウム寄りの性質であれば下向きに垂れ下がります。もちろん、上向きの葉も下向きに垂れ下がる葉も両方の性質を備え持つ個体もあります。
栽培難易度は高くなく、むしろ簡単な部類に入ると思います。キッチャクードの交配組合せとなるリドレイもコロナリウムも栽培難易度の高い品種として知られますが、交配して丈夫になっているからなのか、暑さ・蒸れに強く、真夏の高温にも負けません(32℃以下くらいが安心ですが)。
見た目のかっこよさ(独特さ)と管理のしやすさを兼ね備えた優秀な品種です。個人的にはこれが最もお気に入りの品種です。
ビカクシダ・キッチャクードの育て方
ビカクシダ・キッチャクードの育て方と管理方法を詳しくまとめました。
私が実際に2024年6月から管理している環境や方法を可能な限り詳しくまとめましたのでご参考になさってください。
※この管理方法はあくまで私個人のやり方です。ビカクシダの様子を見たり専門家が発信している情報を収集したりして日々アップデートを重ねていますので、全員が全員このやり方が正しい・合っているとは限りません。あらかじめご了承ください。
基本情報
| 品種名 | ビカクシダ・キッチャクード(Platycerium mt.kitshakood) |
| 交配品種名 | Ridleyi x Coronarium(リドレイ×コロナリウム) |
| 自生地 | なし ※交配品種(園芸品種)のため |
| 見た目の特徴 | ・やや上部が長めで葉脈部分の凹凸が深めな貯水葉 ・先端が細かく枝分かれ(分岐)する形の胞子葉は個体差が激しく、個体の性質がリドレイ寄りなら上に立ち上がり、コロナリウム寄りなら下部に垂れ下がる(両方の特徴を兼ね備えた個体もある) |
| 管理する上でのポイント | ・植え替え・株分けなどは4月~6月がおすすめ(これから暖かくなっていく時期なので失敗しづらいです) ・高温や蒸れには割と強く、真夏でも水苔は湿り気味でOKです |
| お迎えした日(管理開始日) | 2024年6月10日 |
| 植え付けるもの | 私の場合は下記どちらかです ・ビカクシダ板付用の板(メルカリで購入)→キッチャクードはこちらに取り付けています ・通風パネル(Amazonやホムセンで購入) |
| 用土 | 水苔のみ |
| 増やし方 | 胞子培養 |
育成環境・育て方(管理方法)
| 難易度(育成の難しさ) | 2:かんたん (1:とてもかんたん~5:とても難しい の5段階評価) |
| 我が家の気候 | ・関東地方の暖地(最高気温38℃/8月、最低気温:-5℃ 2024年データ) ・耐寒性ゾーン:8b(− 9.4°C ~− 6.7°C) |
| 置き場所(管理場所) | ・春(4月~6月):24時間屋外の日陰 ・夏(7月~9月):9時くらいまでは屋外の日陰、日中は室内(2階吹き抜け)、17時以降涼しくなった時点で屋外の日陰 ・秋(10月~11月):24時間屋外の日陰 ・冬(12月~3月):24時間室内(2階吹き抜け) |
| 最適な温度の範囲 | 15℃~32℃くらい |
| 耐暑性(最高温度) | 34℃ |
| 耐寒性(最低温度) | 10℃ |
| 光量(日当たり) | ・直射日光はNG(葉焼けの原因に、最悪そのまま枯れます) ・室内でも十分育ちますが、北側など光がほぼない場所はNG ・つまり、明るい日陰がベストです |
| 風通し | ・屋外:南向きの日陰でよく風があたる場所で管理(南と東が空いたインナーバルコニー) ・室内:サーキュレーターで空気を循環させる(直接風は当てない) ※ビカクシダの育成におすすめのサーキュレーターはこちら |
| 水やり | 葉水:100均の霧吹きで葉からしたたるくらいに濡らします。 ・春(4月~6月):午前中に一度 ・夏(7月~9月):午前中に一度(9時くらいに室内に取り込むまで乾くことを目安に) ・秋(10月~11月):午前中に一度 ・冬(12月~3月):12時~14時頃に気が向いたら(寒がる可能性もあるのであまりあげていません) 水苔の水やり:冬以外は、基本1~2日で完全に乾くくらいサッと水をあげます。 ・春(4月~6月):常温、朝イチか夕方に水苔がカラカラになったら ・夏(7月~9月):常温、朝イチか夕方に水苔がカラカラになったら ・秋(10月~11月):常温、朝イチか夕方に水苔がカラカラになったら ・冬(12月~3月):少しだけ温めた水を、その日一番暖かい時間帯に ※ビカクシダの水やり方法は「ビカクシダの水やり方法【タイミングや頻度・葉水・季節ごとのやり方など徹底網羅】」に詳しくまとめています。 |
| 肥料 | 基本なくても全く問題ありません。水だけでも十分育ち、小さく管理したい人は肥料・活力剤などはあげない方がいいです。 ・春(4月~6月):週1回くらい液肥を規定量の2倍薄めてあげる ・夏(7月~9月):月1~2回くらい活力剤を規定量の2倍薄めてあげる ・秋(10月~11月):週1回くらい液肥を規定量の2倍薄めてあげる ・冬(12月~3月):あげない |
| 害虫対策 | 冬にカイガラムシが特に発生しやすいです。下記症状が出た時点で、カイガラムシを手でこすって取った上で規定量を水に溶いた殺虫剤を吹きかけています。 ・葉の表面にぷっくりした白~茶色のつぶがつく(カイガラムシ本体です) ・ベタベタした透明な液体?が葉や、管理している場所の床や壁などに付く |
ビカクシダ・キッチャクードの成長記録
ここからは私のスマホの中にある写真(統一感がなく見づらくてすみません)と、私のインスタとThreadsの投稿を引用しつつ、ビカクシダ・キッチャクードの成長記録をまとめています。
その日の気温や管理場所、その時点での育て方のポイントや気付いたことなどもまとめていますのでご参考になさってください。
2024年6月10日
ヤフーフリマでリドレイの性質(特徴)を強く持っている個体という観点で探しに探してこだわって選んだ子をお迎えしました。※胞子葉が上に立ち上がり、リドレイのような葉の先端・形状のものであること
すぐに板付けして、水苔を胞子葉ががっつり覆ってキャベツのような見た目にしたかったので、水苔はかなり多めに、かつ高く盛りました。
全体的な印象はこの購入当初からまったく変わっていません。
個体差の激しいキッチャクードは最初の特徴がそのまま残るので、「こんな形が良いな」という理想形がある方は、ある程度成長している中型以上の株で、その子の特徴・性質がはっきり出ているものの中から好みのものを厳選するのがおすすめです。

2024年6月21日
順調に成長し、すぐに貯水葉が出てきました。小さいうちからキッチャクードの特徴である葉脈の深い凹凸が出ていてほんとうにキャベツのようです。

2024年7月18日
前回から1ヶ月近く経過し、我が家にお迎えしてから最初の貯水葉が水苔の左側をすべて覆い隠すくらいまでに成長しました。
見た目ほぼリドレイのようですが、貯水葉の上側が尖るように長くなるのがキッチャクードの特徴なんだなあと思った記憶があります。このへんがコロナリウムとの交配種ならではですね。

2024年9月12日
貯水葉が成長しきったあとは胞子葉ターンに突入して、写真ないのが恐縮なのですが8月中には右側にはお迎えしてから最初の胞子葉が展開。そして9月からは下記写真にあるように左側にさらに胞子葉の新芽が出てきました。キッチャクードは最初のうちから先端が分岐した胞子葉で、まるで赤ちゃんの手のような雰囲気でかわいいです。
貯水葉・胞子葉が左右に生え揃って、このあたりから非常に見栄えのする形になってきました。最初からある程度の大きさの株を購入すれば、3ヶ月くらいでかなり形が整うようです。ご参考に。


2024年9月30日
左側に展開した新芽が成長してさらに見栄えするようになりました。1ヶ月弱でここまで育つので、やはりキッチャクードは高温・多湿を好むことがわかります。

2024年10月14日
パッと見た感じはわかりづらいのですが、2週間経過してさらに左側の胞子葉が成長しました。さすがに秋に入ると成長が少し鈍化してきます。

2025年4月22日:初の胞子嚢つきの胞子葉が!
前回更新からかなり飛びました。
春になって右側の胞子葉に新芽が展開してきたのですが、最初のうちから「あれ?なにかこの葉っぱ今までと形状が違うぞ・・・」と思っていたら、胞子嚢つきの葉っぱ・通称「スプーン」でした。ビカクシダを育て始めて初のことだったのでとてもわくわくしました。
※わかりづらいのですが、写真中央やや上のハート側の葉っぱがそれです。
冬の間はリビングにずっと置いているのですが、それである程度の温度がキープできたこともあってか順調に成長を続けて株が充実したのかなと思います。

2025年7月10日:さらに胞子嚢つきの胞子葉が出てくる
お迎えしてから1年と1ヶ月。
季節は夏になり、気候が合ってきてぐんぐんと成長。非常にわかりづらいのですが、左側に展開した胞子葉にもハート型の胞子嚢つきの葉っぱをつけていて、上記で書いた最初の胞子葉にはすでに胞子が少し付いています(茶色の部分がそれです)。
さらに貯水葉も新たに右側に展開してややワイルドな容貌になってきました。

2025年8月7日:理想通りのフォルムのキッチャクードに
7月に展開してきた右側の貯水葉が充実して、かなり完成された姿に。
この時のキッチャクードは最初に「キッチャクードがほしい!」と思ったときの理想通りの姿に育ってくれて本当に感動的でした。
※このあと右側手前の胞子葉が枯れて落ちてしまうのですが・・・(黄色くなっている葉っぱです)

2025年9月3日:貯水葉が順調に成長、胞子葉の葉先がやや枯れ


上記で書いたように右側手前の胞子葉が枯れて取れてしまったものの、相変わらず形は理想的。今度は貯水葉ターンに突入して左側に新しい葉っぱが展開してきました。
気になるのは胞子葉の葉先の枯れてきていること。原因は恐らく水分不足かなと思っているので、下記のように管理をアップデートしてみようと思います。(このキッチャクードの一番のお気に入りである胞子葉の形をキープするためにも)
- 朝:したたるくらいに葉水をたっぷり
- 夕方:真っ暗になるまで完全に乾くくらい軽めに葉水
Threadsで見る
2025年9月12日:貯水葉がさらに成長、わずか10日間で3~4倍の大きさに




9月に入ってもまだ35℃近くの気温が続く中でも暑さ・湿度が好きなキッチャクードはすくすく成長中。気になっていた葉先の枯れも、葉水を忘れずにあげていることと、9月2週目以降になって雨だったりで湿度の高い日が続くことが幸いしてか致命的な感じになってはいないようです。
左側に展開した胞子葉はさらに大きくなり、前回UP時より3~4倍の大きさ(10日で3~4倍)に成長しました。この時期の成長速度は目を見張るものがありますね。
Threadsで見る
2025年10月8日:左側の貯水葉が順調に成長、さらに次の貯水葉が展開




前回から1ヶ月近くが経過し、左側の貯水葉はぐんぐん成長して水苔を完全に覆い尽くしまして、板に張り付くように伸びていっています。さらに成長が続くかもしれません。
そして今度は右側に新たに貯水葉が展開し、すでに直径4cmほどにまでなっています。
さらに成長点には次の新芽も見えていてこれはおそらく胞子葉かな?と思っています。
ちなみに胞子葉の葉先が枯れるのはゆっくりになってきています(葉水のおかげ?)
秋に入ってやや成長は鈍化しているように感じますが、とりあえず11月頭までは夏と変わらずに水苔をしっかり濡らして湿度多めの状態をキープする水やりをしてみようと思います。
Threadsで見る
ビカクシダ・キッチャクードを育てる上でのFAQ
キッチャクードとリドレイの違いは?
ビカクシダ・キッチャクードとビカクシダ・リドレイの違いは、キッチャクードはリドレイとコロナリウムをかけ合わせ交配させた園芸品種であるのに対し、リドレイは原種で東南アジアのボルネオ島などに自生しています。
見た目や育て方などの違いは下記をご覧ください。
| 項目 | キッチャクード (Mt. Kitshakood) | リドレイ (Ridleyi) |
| 分類 | リドレイ×コロナリウムの交配させた園芸種 | 原種(東南アジアのボルネオ島などに自生) |
| 胞子葉 | ・細かく分岐するが、リドレイ寄りのものであれば上向きに立ち上がり、コロナリウム寄りであれば下向きに垂れ下がる・どちらかの葉の種類に偏ることもあれば両方を備えることもあり、個体差が激しい | シカの角のように丈夫に立ち上がり細かく分岐する |
| 貯水葉 | ・リドレイに似た葉脈にそって凸凹のあるキャベツのような見た目・上側がやや細長くなる形状 | ・キッチャクードよりも凸凹がより深く細かい・正円状に丸っこい形状 |
| サイズ | 中型~やや大型(コロナリウム寄りであれば下に垂れ下がる方向に大きくなる) | 中型(約40~50cmくらいが一般的) |
| 耐寒性/耐乾性 | 比較的強い(最低気温10℃程度) | 弱い(最低気温15℃程度が安心) |
| 育てやすさ・難易度 | 比較的かんたん | 難しい |
| 耐暑性 | 34℃程度高温・多湿を好み、日本の真夏にも耐えられる | 32℃程度高温には強いが蒸れに非常に弱いので風通しの良さは必須 |
キッチャクードの大きさは?
キッチャクードは中型~やや大型になる品種で、その株がリドレイ寄りかコロナリウム寄りかで最大の大きさはだいぶ異なります。(胞子葉が上向きか垂れ下がるかで特に縦の大きさが変わります)
リドレイ寄りであれば50cm前後、コロナリウムであれば縦に1Mを超えることもあるようです。
キッチャクードの越冬方法は?
おうちの中で最も気温変化の少ない場所(つまりエアコンや暖房器具を設置してある場所、リビングなど)においておけば、特に問題なく冬は越せると思います。私の所有しているキッチャクードはリビング東側の窓付近に壁がけした状態で冬越しに成功しました。
ちなみに越冬温度の目安は最低10℃以上をキープすると安心です。
水やりは、上記でも説明していますが少しだけ温めた水を、その日一番暖かい時間帯にあげると安心です。また、肥料は冬はあげないことをおすすめします(成長鈍化するので必要なくなるため)
キッチャクードは難しい?育てやすい?
キッチャクードは難しいという意見もありますが、私個人は比較的育てやすい簡単な部類に入る種だと思っています。
まず夏の管理が比較的楽で、高温多湿を好む時点で日本向きです。冬も上記のようにリビングなど温度変化が少ない部屋に置きっぱなしでOKですので管理は楽です。
キッチャクードが成長しないのはなぜ?
キッチャクードが成長しないのはいくつか原因が考えられ、一概にこれというものはありません。
- 環境に慣れていない(お迎えしてから間もない)
- 水が足りない
- 水を上げすぎて根腐れを起こしている
- 光量が足りない
- 暑すぎる
- 寒すぎる
- カイガラムシなどの病害虫による被害
など様々な要因が重なっていることが多いです。私の管理している環境は上記で説明しています。これが今のところ私が育てていて最適だと思う環境ですので、まずはそれとの違いが何なのかを見比べてみてください。
キッチャクードは子株で増える?子株を出す?
キッチャクードはリドレイの血をひいていることもあってか、基本的には子株を出さない品種だと思われます。
たまにフリマで「ビカクシダ・キッチャクード 子株」のような商品名で出品されていることがありますが、それは「小さい株」の言い間違いであって、胞子培養で増やしたものであると考えられます。
キッチャクードの板付方法は?
ビカクシダ・キッチャクードも他のビカクシダの品種と同じように板付けしても構いません。
ですが、私個人はキッチャクードは貯水葉のユニークさが大きな特長で傷つけたくないと思っているので貯水葉の上からテグスを巻くことはせずに、貯水葉をやさしくめくってその下にある水苔のみをテグスで巻いて固定してから、板に結束バンドなどで固定する方法で板付しています。
※2024年6月21日の写真は板付直後の様子ですが、テグスが貯水葉の上に巻かれていないことがわかると思います。
この方法であれば最初から見栄えの良い状態でキッチャクードを愛でられますし、今のところテグス等がほどけて株が落ちてくる等の事故も起きていません。
テグスを貯水葉の上から巻き付ける板付け方法は手軽でしっかり固定できるのは良いのですが、反面どうしても見栄えが悪いのが大きなデメリットです。
せっかくお気に入りのビカクシダを飾るのであれば見栄えの良さも重視したいものです。