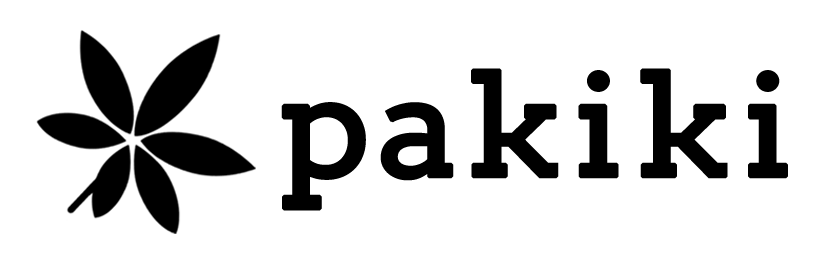このページではビカクシダの水やり方法について詳しく解説しています。
ビカクシダの育て方で最大のポイントともいえる「水やり」。水やり方法の基本から、季節ごと水やりの方法、水やりのタイミング(水切れのサイン)や頻度など必要だと思ったことはすべてまとめています。どうぞご参考になさってください。
※ただし、ここでご紹介する方法が正解ではありません(すべての人に適しているわけではありません)。各個人の住宅事情だったり、ビカクシダの種類や数、天候などにより適した水やり方法は異なります。下記に挙げた私のビカクシダの育成環境に近い方向けの方法となるかと思いますのであらかじめご了承いただき、「これなら自分の家でも適していそうだな」と思った部分だけ参考にしていただくのが良いと思います。
| 気候 | ・関東地方の暖地(最高気温38℃/8月、最低気温:-5℃/1月 2024年データ)・耐寒性ゾーン:8b(− 9.4°C ~− 6.7°C) |
| 置き場所(管理場所) | ・春(4月~6月):24時間屋外の日陰・夏(7月~9月):9時くらいまでは屋外の日陰、日中は室内(2階吹き抜け)、17時以降涼しくなった時点で屋外の日陰・秋(10月~11月):24時間屋外の日陰・冬(12月~3月):24時間室内(2階吹き抜け) |
| ビカクシダの数 | 10株以上~ |
| 間取り | 一戸建て・4LDK |
| 水やりしている場所 | インナーバルコニー(屋根付きのバルコニー) |
ビカクシダの水やりは大きく2つ:「葉水」と「用土への水やり」
ビカクシダの水やり方法は、他の観葉植物と同様に主に2種類あります。
霧吹きなどで葉っぱを濡らす「葉水」と、いわゆる「水やり」と一般的にいわれる用土を濡らす水やりの2つです。
葉水

葉水は字のとおり葉っぱ(胞子葉・貯水葉)を濡らす水やり方法です。
メインの目的は葉っぱの乾燥を防ぐためですが、他にもハダニなどの害虫を予防する目的、葉面に付着するホコリや汚れを落とすことで美観を維持したり光合成を促進するなどの目的もあります。
葉水のコツは表面だけでなく裏面まで行うこと。ビカクシダに限らず植物は葉の裏にも気孔と呼ばれる蒸散や呼吸をするための器官があります。気孔は根の水分吸収が少なく、葉が多少しおれ気味のときに水を吸収したりもしますので、特に乾燥気味の時期や夏の暑い時期などは葉裏への水やり(葉水)は重要です。
用土(水苔など)の水やり

もうひとつは用土(ビカクシダの場合は主に水苔)を湿らせるために行う水やりです。
ビカクシダに限らず観葉植物全般への水やりは一般的にこの用土を湿らせる水やりのことを言うと思います。
植物は根っこから水分や養分を主に吸収しますので、水やりの方法をちゃんと知っておくことは植物の健康的な成長のためには必要不可欠です。
用土(水苔など)の水やり方法についてはこのあと詳しく説明します。
ビカクシダの用土(水苔)の水やり方法3種類
ビカクシダの用土(水苔など)の水やり方法は主に下記3つです。
- シャワーやじょうろ、水差しで水苔にかける方法
- 水をたっぷり張ったバケツなどにドボンとつける方法
- 雨ざらしにする方法
それぞれやり方とメリット・デメリットを説明します。できれば全部ためしていただいてご自分に合ったものを選んでみてください。
シャワーやじょうろ、水差しで水苔にかける方法
水をドバーッと水苔にかける方法です。
私の水やり方法はこれで、水苔の10~20cmくらい上から水差しに入れた水をドバーっとかけています。(バケツに水を張って、そこから少量ずつ汲みながらやっています)
ベランダやお庭がなかったり、一人暮らしの方などは洗面所やお風呂でシャワーを使ってザーッと水やりをしてもOKです。
メリット
- 水苔の重さを確認しながら水やりできる
- 病気や害虫が伝染しにくい
私の場合は板ごと手に持って水やりをしているので、徐々に水苔が水を含むのを確認しながらできるため重さを確認できるというのが一番のメリットだなと思っています。
また、シャワーを使ってやる場合は後述する「雨ざらし」の状態を再現することにもなるのでそれもメリットといえると思います。
デメリット
- やや時間がかかる
- 水道代がかかりすぎることも
- 疲れる
逆にデメリットは時間とお金がかかることです。
動画にあるように、ビカクシダを着生させた用土(水苔)にドボドボを水をかけるので、ドボンとつける方法に比べてどうしたって水を無駄にしてしまいますし、効率的に水を与えられるわけではないので時間もかかります。
加えて、ひと株ずつ手に持って水やりするので500g~1kgくらいになるビカクシダを10株以上やるとやっぱり疲れます。
水をたっぷり張ったバケツなどにドボンとつける方法
バケツなどにビカクシダを着生させた板や流木、鉢や苔玉ごとすべて浸るくらいにたっぷりと水を張り、その中にドボンと入れてしまう方法です。
水苔の場合は水やりの間じゅう、ぶくぶくと泡が出てきます。このぶくぶくと泡が立たなくなるまでやると完全に水苔が水を含んだ状態ですのでこれを基準にして調整するといいでしょう。
メリット
- 放置でOKなのでかんたん(ドボンと沈めておくだけなので)
- 水道代が節約できる
- 疲れにくい
たっぷりの水にドボンとするだけなので水道代は節約できますし、かんたんです。
上記のようにぶくぶくと泡が出なくなるまで放置すればいいという手軽さも良いですよね。
また、板付けされた株を持っていることもないので疲れません。私も最初はこの水やり方法をやっていました。
デメリット
- 病気や害虫が伝染しやすい(同じ水を使うため)
- ビカクシダが丸ごと入るバケツなどの容器が大きい、かつ重い
逆にデメリットは何株も同じ水を使って水やりをするので、病気や害虫が伝染しやすいということです。
最初に病気や害虫がいるビカクシダをバケツにドボンと沈めて水やり→その後、その同じバケツ内にドボンとしたビカクシダにはすべて病気・害虫が伝染するリスクが高いわけです。実は私はこれを体験して、この水やり方法をやめた一人です。(ちなみにハダニ)
また、ビカクシダが入るほどのバケツとなるとそれなりの大きさになりますし、ビカクシダが成長するに連れて容器の大きさも大きくしなければならないのもデメリットです。
その分水道代はかかりますし、バケツを置く場所も取るのでこのへんもデメリットといえます。
雨ざらしにする方法

最後に、ただ雨を当てるだけの簡単な方法です。(雨の日に、雨が当たるところにビカクシダを出すだけ)
本来ビカクシダは木や岩などに着生して、主に雨水で水分補給をしているわけなので、ある意味最も自生地に近い自然な形の水やりといえます。
ただし、梅雨など雨が長く続く時期は、連続して2日(48時間)までにとどめておくのがコツです。それ以上連続して雨ざらしにしてしまうと、水苔などの用土が乾きづらく、根腐れの原因や害虫発生のリスクが上がってしまいます。
Threadsで見る
メリット
- 天然の栄養素も同時供給するので生き生きする(肥料が要らない)
- 葉水の効果も同時に得られる
- 水道代がかからない
- 最も手軽
前述のように最も自生地に近い自然な形での水やりですので、もしできるならこれがベストな水やり方法です。
そもそも雨は塩素などを含みませんし、空気中の窒素などの微量栄養素を含みながら水分と同時に供給してくれるので生育には最適な水になります(つまり肥料が不要)。
雨あがりの植物は、ビカクシダに限らずどれも葉がピンとして見るからに生き生きしているので私は雨が降ると必ず外に出して雨に当てるようにしています。
デメリット
- 水切りが大変
- いつ雨が降るかそもそもわからない
- 激しい雨や暴風を伴う場合は大ダメージを受けることがある
できるならベストと言いましたが、デメリットももちろんあります。
全体がビショビショに濡れてしまうので中にしまう際に水切りするのが大変ですし、激しい雨や暴風を伴う場合は葉が折れたりなどダメージを受けることもあります(特にまだ小さい株は)
また、水苔が乾燥しきっていて今水やりしたい!というタイミングで雨が降るなんてことはほぼないので、そもそもいつ降るかわからないというのは最大のデメリットです。
とはいえ、上記2つの通常の水やりと並行して絶対に試してほしい水やり方法です。
ビカクシダの水やり方法4つの手順
次にビカクシダの水やり手順ですが、私の水やり方法の手順を4ステップでご紹介します。
ちなみに私の自宅の環境は冒頭でご紹介したとおりです。これと同じか似た環境の場合は私のやり方が参考になるかと思いますが、逆に異なる環境の場合は「この部分は自分の家でもできそうかな」くらいのスタンスでご覧いただくとよいと思います。
①水苔が乾いていることを確認する

まずはビカクシダの用土(水苔)を触って、乾いているかどうかを確認します。
乾いた状態の水苔は、硬く、カサカサした手触りなのですぐにわかると思います。水苔がこの手触りになった状態だったら、そのビカクシダは水やりが必要な状態で、水のやり時だといえます。
逆に水苔を触った感じが、柔らかい(押すと水分が出てきたり水を感じる)、しっとり
したりひんやりした状態だったら、そのビカクシダは水やりが不要です。
なお、ビカクシダは品種によって乾燥に強い・弱いの差がありますので、水苔が完全に乾き切る前にやった方がいい品種も中には存在します。
ですが、基本は他の観葉植物と同じく、しっかり用土が乾いたら水をたっぷりやる、が定石ですので、まずはこの基準でいいと思います(特にネザーランドやビフルカツムといった初心者向けの品種についてはこのタイミングで問題ありません)
②水やり場所に道具と水やりが必要なビカクシダを集める

次に水やりをするのに適した場所に、バケツや水差しなどの道具と、水やりが必要なビカクシダを持っていきます。
水やりに適した場所=水で濡れたり、水やり後に水苔が落ちても大丈夫な場所のこと。たとえばお風呂場だったり、私の場合は直射日光も当たらず防水処理もされているインナーバルコニー(屋根付きのバルコニー)にしています。
私がビカクシダの水やりに使っている道具は下記の通りです。
- TRUSCOのバケツ(15l)
- 水差し(確か15年くらい前に100均で買ったもの)
- 雑巾(板の水拭き用)
ちなみにお風呂場で、シャワーを使ってジャバジャバと水やりをする場合はこれらの道具は不要です。
③水やりする
あとは1株ずつ水やりをしていくだけです。
上記動画にあるように、水苔が出ている部分を狙って割と勢いよくドバドバと水差しで水をかけていきます。300ml以上入ると思われる水差しで約2~3杯分をかけます。
後述しますが、最長でも2~3日くらいで完全に水苔が乾くくらいの水をあげましょう。私の場合はこれが2~3日くらいで完全に水苔が乾くくらいの量になりますが、使う道具や環境によって水やりすべき水量は異なりますので、ご自身の環境に合わせて試して調整してみてください。
最初は水が足りないかな?くらいの少なめの量で試して、増減させていくのがおすすめです。
④水切りする

最後に水切りして終了です。
板付けされているなら、立てかけたり吊るしたりして水が垂れなくなるまでしばらく「日陰」で放っておきましょう。(直射日光が当たると葉焼け…最悪、枯れの原因にもなりますのでご注意ください)
早く済ませたい場合は雑巾などで吹いてしまいましょう。
私の場合はインナーバルコニーに設置してあるビカクシダウォールにそのまま吊り下げてしまいます(ふだんビカクシダを飾って管理してある場所)
ビカクシダの水やりのタイミング
上記で水やりに適したタイミングについて少し触れましたが、ここではより具体的にビカクシダの水やりのタイミングを見極める方法について書いていきます。
基本は「水苔が乾いたら」水やりする
先述のように基本は「水苔が乾いたら」水やりです。
水苔が乾いたかどうかは、指で触り目で見て確認するトリプルチェック法です。下記3つの観点で確かめて、どちらにおいても「水苔が乾いている」と判断できるときが水やりのベストタイミングと言えます。
触って水やりが必要か確認する(水苔も葉も)

まずは触った感触ですが、前述のように乾いた状態の水苔は、硬く、表面が毛羽立ってカサカサした手触りなので触ればすぐにわかると思います。
またこれも前述のように、これとは逆に水苔を触って柔らかかったり、しっとり・ひんやりした状態だったら、水苔はまだ湿っていて水やりが不要な状態です(押すと水分が出てきたり水を感じる)。

加えて胞子葉・貯水葉を触るのも大事です。触ってピンとした張りを感じたりひんやり瑞々しい状態だとすれば水やりは不要。逆に柔らかかったりややカサカサするような感触を覚えれば水やりのタイミングです。
水苔だけでもまったく問題はないのですが、意外に葉っぱも水不足かどうかは判別できるので念のため書かせていただきました。
目で見て水やりが必要か確認する(濃いか薄いか)


次に見た目ですが、これは上の写真のように比較してみるとわかるのですが、左のように水苔自体の色が薄い場合は水苔が乾いた状態ですので水やりが必要です。
右のように色が濃い状態だったら濡れている(湿っている)状態ですので水やりは不要になります。
持って重さを確認する
最後に重さです。水苔が水をたっぷり含んだ株と、カラカラに水苔が乾いた株では最大で2倍くらい重さが違います。
特にまだ小さい株ではこの差が顕著です。ほぼほぼ水苔に含まれる水分量でその株の重さが決まりますので、明らかに持ったときに差が出ます。
ただしビカクシダの品種によっては持ったときに明らかに「軽い!」となったときはすでに水切れして手遅れ的なこともありますので(水切れに弱い品種:リドレイやアンディナムなど)、注意が必要です。
水苔を触った段階で乾いているのがわかればすぐにあげるくらいでも問題ないです。
ビカクシダの水やりで気をつけるべきポイント
次にビカクシダに水をやるときの注意点です。いくつかありますのでこちらも合わせて見ておいていただけるといいと思います。
2~3日に1回、1週間に1回などルーティン化した水やりはNG
まずはルーティーン化した水やりについてです。
よくあるのが「2~3日に1回水をあげればOKです」などの記述などですが、個人的にはこれは絶対に避けるべきNGな水やりです。
気温・湿度が1年中ずっと安定している環境下なら話は別なのですが、一般的に日本というのは春・秋が気候が安定しており、夏は暑く湿度が高く、逆に冬は寒くて乾燥します。
このように気象条件が季節ごとで変化します(日ごとで大きく変わることも珍しくありません)ので、水苔が乾く速度もまったく違います。
夏は半日でカラカラになることもあれば、冬は1週間近く乾かないこともあります。
それなのに「ビカクシダ2~3日に1回水をあげればOKです」というのはあまりに乱暴で、夏は水切れになって株が弱る可能性がありますし、冬は水苔が乾かず根腐れになったり、寒気に当たれば濡れた水苔の影響で余計に寒がって枯れてしまうリスクが高まります。
水やりのタイミングは上記のようにあくまでも「水苔が乾いたら」です。
ちなみにこれはビカクシダに限らず観葉植物全般に言えることです。2~3日に1回、1週間に1回などルーティン化した水やりは絶対にやめましょう。
長くても2~3日で乾くくらいにサッと水やりする
次に水やりの際にあげる水の量ですが、目安は長くても2~3日で乾くくらいの量です。
ビカクシダに限らず観葉植物全般に言えることなのですが、植物の用土は「乾・湿」のサイクルが早い方が良いとされています。(だから水はけの良い土が良い土と言われるんですね)
そのため可能であれば1日で完全に乾く量がおすすめなのですが、毎日水やりをするのはさすがに大変ですので(数が増えれば増えるほど手間も時間もかかりますし)、2日か3日では完全に乾くくらいの量がおすすめです。
それ以上経つと、水のやり過ぎによる根腐れのリスクが高まりますので、最長でも3日くらいにとどめておくのがいいと思います。
具体的に何mlがおすすめです、と書かないのは個々の住宅環境によって温度・湿度の状態が全然違うためです。
まずは「ちょっと少ないかな」と思うくらいの量を与えて水苔を濡らしてみて、それが1日で乾くならもう少し水の量を増やしてみる…等してご自身で自宅とビカクシダのいる環境に合った水量を見つけてみてください。
葉水は毎朝10時頃までに1時間くらいで乾く量をあげる
最後に葉水についての注意点です。
葉水はと書きましたが、与えすぎてもいけません。葉水がずっと乾かずビカクシダの葉に水滴がついたままの状態が続くと、湿度が高い状態が続くことになりますのでカビや真菌が繁殖しやすい環境になります。
特に、夜間や日当たりが悪く風通しの悪い場所では、このリスクが高まりますので注意が必要です。
そのためおすすめなのが「毎朝10時頃までに1時間くらいで乾く量をあげる」ことです。
ちなみに「1時間くらいで乾く量」の目安ですが、私の場合は下記のようにしています。
- 春・夏・秋:水滴が葉先から滴り落ちるくらい
- 冬:表面がうっすら濡れているのがわかる程度

水滴が葉先から滴り落ちるくらい葉水を

表面がうっすら濡れているのがわかる程度に葉水を
このくらいの量であれば1時間くらいで完全に乾くと思います。ただしこれも個々の環境によって変わりますので、上記を目安として自宅ではどうなのか必ず試してみてください。
ビカクシダの水やりに関するFAQ
ビカクシダの水切れのサインは?
ビカクシダの水切れのサインは主に胞子葉に現れます。胞子葉がしおれたり、ピンとしていたものが元気なく垂れ下がったりしたときは水切れのサインです。ふにゃふにゃと手で触っても柔らかかったりしますので、触ってみるとわかりやすいと思います。
※なお、この際はもちろん水苔も触って乾いてカサカサして硬いかどうかを確認しましょう。胞子葉がしおれてふにゃふにゃしていたとしても、水苔が濡れていたとすればそれは水切れではなく「根腐れ」の可能性が高いからです。
なお、胞子葉がしおれてふにゃふにゃするのは細胞内の水分が不足し、葉が自身の重さを支えられなくなるため起こる症状です。すぐに水苔をたっぷり濡らしてあげて、かつ霧吹きによる葉水も行いましょう。
次に貯水葉に起こる変化ですが、貯水葉が乾燥してシワが寄ったりへこんだりすることがあります。貯水葉は水分を蓄える「タンク」にあたる役割がある葉っぱですので、この部分にまで水切れのサインが出るのはかなり長期間水やりしていない場合くらいです。
以上のように、基本的には胞子葉が元気なく垂れてきて柔らかい状態で、かつ水苔など用土が乾いていれば、ビカクシダの水切れのサインと考えていいでしょう。
ビカクシダは夜に水をやってもOK?
結論、ビカクシダは夜に水やりをしても問題ありません。ですが、夜に水をやることのリスクもあることを覚えておきましょう。
「夏の高温対策」としては夜の水やりはおすすめなのですが、夜温が15度を切るくらいの時期に夜間に水やりをすると、水苔などの用土が湿った状態が長く続きます。そのため寒がって枯れてしまうリスクもあれば、低温・高湿度の状態が長く続くことでのカビや病害のリスクも出てきてしまいます。
そのため、もしどうしても夜にしか水やりができないということであればサーキュレーターを使って風通しを確保することが不可欠です。
なお、ビカクシダ育成におすすめのサーキュレーターは下記の記事にまとめていますので合わせてお読みください。ちなみに私個人の最もおすすめのサーキュレーターはボルネードの「633DC-JP」です。
※関連記事:ビカクシダの管理・育成におすすめのサーキュレーター【選び方・メリット・使い方も解説】
ビカクシダは水をやりすぎるとどうなる?
前述していまうが、ビカクシダは水をやりすぎると水苔が乾かず濡れたままになるため、呼吸ができず「根腐れ」を起こしてしまい、そのまま枯れてしまうことが非常に多いです。
これはビカクシダにとっては水切れ以上に致命的な問題ですので、繰り返し言っているように「長くても2~3日で乾くくらいに少なめに水をやる」のがビカクシダの水やりをする上でのコツです。